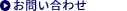グローバル HR ソリューションサイト
by Link and Motivation Group
- グループサイト
-
文字サイズ
2020.05.07
名作にみる美しい英語(164)
原島 一男
“I would like a medium Vodka dry Martini
- with a slice of lemon peel.
Shaken and not stirred please.”
(Ian Fleming: Doctor No )
「ミディアム・ドライのウォッカ・マティーニ。
それにレモン・ピールをひと切れ入れてください。
ステァしないで、シェークするだけで」
(イアン・フレミング作 「ドクター ノオ」)
小説や映画などの名作から選んだ英語を紹介する連載。
そのフレーズが生まれた時代や背景を色濃く伝え、使った人の気持ちを具体的に表します。
それをじっくり観察することで、あなたの今の英語を鍛えあげましょう。
言うまでもなく、一つのフレーズだけでは、その作品の全貌をつかむことはできません。
しかし、それが、あなたの感性を刺激することもあるかもしれません。
イギリス政府の諜報部員007ジェームズ・ボンドが映画史上に初めて登場したのは1962年。
東京オリンピックの2年前です。原作は元イギリス海軍諜報部の将校だったイアン・フレミング。
21世紀まで続く 007(ダブル・オー・セブン)シリーズ でジェームズ・ボンドは世界を魅了、高性能の車、美しい女性、趣味の良いファッション、超先端技術を駆使した兵器、それに度肝を抜かれる活劇シーンはすべての男性の憧れで、日本を舞台にした「007は二度死ぬ」(You Live Only Twice 1967)には、ボンドガールとして浜美枝さんや若林映子さんも出演しました。
シリーズ第1作の映画「ドクター ノオ」で交わされたこの台詞はカクテルのマティーニを世界中に広めましたが、映画の台詞はオリジナルとほとんど同じです。ただ微妙な違いが見られます。
DOCTOR NO: A medium dry martini, 「ミディアム・ドライのマティーニ。レモン・ピールひと切れ。
lemon peel, shaken not stirred. ステァしないで、シェークして」
JAMES BOND: Vodka? 「ウォッカで」
DOCTOR NO: Of course. 「もちろん」
ー「007 ドクター・ノオ ー007 は殺しの番号 (Doctor No 1962 監督:テレンス・ヤング
脚本:リチャード・メイバウム、ジョハナ・ハーウド、バークリー・マサー 原作:イアン・フレミング)
この同じ台詞 "A Martini. Shaken, not stirred." は、3作目の映画「007/ゴールドフィンガー」にも出てきます。
悪党側に捕らえられ意識を失ったジェームス・ボンド(ショーン・コネリー)でしたが、我に返ると飛行機の中、目の前には妖艶な姿のプシー・ギャロア(オナー・ブラックマン)が。
JAMES BOND: Who are you? 「あなたはどなた?」
PUSSY GALORE: My name is Pussy Galore. 「プシー・ギャロアというものです」
JAMES BOND: I must be dreaming.... 「きっと夢を見ているんだ、、、
By the way, where is here? さてと、ここはどこかな?」
PUSSY GALORE: We're flying over southwest of New Zealand.
「ニュージーランドの南西を飛行中です」
GIRL: Can I do something for you, Mr. Bond?「ボンドさん、何か差し上げましょうか?」
JAMES BOND: Just a drink. 「飲み物をください。
A Martini. Shaken, not stirred. マティーニを。ステァしないで、シェークして。
Won't you join me? 一緒につき合いませんか?」
PUSSY GALORE: I'm on duty. 「私、仕事中です。
Mr. Goldfinger's personal pilot. ゴールドフィンガー氏の個人パイロットです」
-「007ゴールドフィンガー」 (Goldfinger 1964 監督:ガイ・ハミルトン 脚本:リチャード・メイバウム、ポール・デーン)
・I must be dreaming. =「私は夢を見ているに違いない」→ 「きっと夢を見ているんだ」
・Can I do something for you? =「何か差し上げましょうか?」相手にものを勧める定形表現
・ここの shaken/stirred は過去分子形。つまり、martini を修飾して「shake された」「stir された」 となり、shaken, not stirred は「スプーンなどでかき混ぜないで(シェーカーを使って)シェークしたマティーニ」という意味
cf:“She put butter in her coffee and stirred it . 「彼女はバターをコーヒーに入れてかき回した」
“Shaken but not stirred situation” 「揺れているがそれほどの影響を与えない状況」
“Look at the girl dressed in green.” 「あの緑色のドレスを着た少女を見てごらん」
マティーニはジンにドライ・ベルモットを少し入れ、ステァだけでシェークしないのが普通のつくり方です。
それを、あえてシェークして、というところがボンド流なのです。
shake (シェーカーを使って混ぜる)と stir(かき混ぜる)の違いをひと言で言うと、shake すると飲み物の中に空気が入るので、まろやかな刺激のない味になり、stir のほうは冷たさが舌に直接感じてより刺激の強い味わいになる、といわれます。
いずれにせよ、マティーニの造り方は多種多様であり、ジン、ウオッカ、ラムのベースとベルモットの比率もまちまち。
ベルモットのかわりに日本酒を入れる Saketini もあります。最近になって強いお酒は流行らなくなりましたけど、マティーニほど人々の心を捕えたカクテルは、後にも先にもなかったと言ってよく、20世期のハリウッド映画はマティーニに明け暮れました。
マティーニにまつわるもう一つの映画のシーン。
STEWARD: Cocktail before dinner, sir. 「ディナーの前のカクテルをいかがですか」
ROGER: Yes. A Gibson, please. 「ギブソンを」
STEWARD: Right away. 「かしこまりました」
ー「北北西へ進路を取れ」(North by Northwest 1959 監督:アルフレッド・ヒチコック 脚本:アーネスト・レーマン)
この映画でケーリー・グラントがニューヨーク発シカゴ行きの列車に乗り、食堂車で注文するのがギブソンというカクテル。
マティーニとどこが違うのかというと、マティーニはガーニッシュ(Garnish 付け合わせ)として、オリーブかレモンの皮を添えるのですが、ギブソンはパーテイ・オニオンを添えます。
「ユーガットメイル」では、トム・ライアンがモーターボートの中で父親にカクテルを作りますが、父親にはギブソンを作りパーティ・オニオンを入れ、自分のにはオリーブを入れたマティーニを作っています。
パーティ・オニオンが手に入らないときは、’日本のらっきょう’ で代用できますけど。
「花嫁の父」では、”Martini? Is that your drink?’(マティーニはあなたのお酒ですね)という会話がありますし、「7年目の浮気」では、マリリン・モンローが「私の故郷コロラド州デンバーではマティーニにお砂糖をたくさん入れるのよ」( Back home In Denver, Colorado, they put sugar in martinis a lot. )と言って、観客を大笑いさせます。
この映画を作ったのはビリー・ワイルダー。
彼は「昼下がりの情事」の撮影のとき、パリで泊まったホテルのマティーニの味が気に入らないとホテルを換えたほどマティーニを愛していました。そのときパリに居たオードリー・ヘプバーンは、パリで飲んだマティーニを「すごくドライで冷たくてとっても美味しかった」と言っていましたが。
ところで、マティーニ(ギブソン)の作り方は、ジンにドライ・ベルモットを少し入れるだけ。
適量といっても、ベルモットをほんの1滴という人もいるし、「ジン:9、ベルモット:1」、「ジン:15、ベルモット:1」を主張する人、それに氷の触れ合う音が好きなオン・ザ・ロック派もいます。
マティーニがこれほどまでに‘こだわり’の対象になった最大の理由は、ベルモットの量やかき回し方によって微妙に変わる‘自分の味’が作れるからではないでしょうか。
―――
原島一男著「心をなごませる感じのよい英会話」(ベレ出版) 好評発売中
原島一男著「単語で通じる英会話」 (ベレ出版) 好評発売中
原島一男著「映画のなかのちょっといい英語」(麗澤大学出版)好評発売中

-
原島 一男
Kazuo Harashima

一般社団法人内外メディア研究会理事長、ノンフィクション作家。慶應義塾大学経済学部卒業。ボストン大学大学院コミュニケーション学科に留学後、1959年NHKに入局。国際局で英語ニュース記者・チーフプロデューサーを務める。定年退職後、山一電機株式会社に入社、取締役・経営企画部長などを務める。現在、英語・自動車・オーディオ関連の単行本や雑誌連載の執筆に専念。日本記者クラブ・日本ペンクラブ会員。『店員さんの英会話ハンドブック』(ベレ出版)、『オードリーのように英語を話したい!』(ジャパン・タイムズ)、『なんといってもメルセデス』(マネジメント社)など、著書多数。