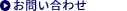グローバル HR ソリューションサイト
by Link and Motivation Group
- グループサイト
-
文字サイズ
2017.07.31
【グローバル人事管理の眼と心(31)】人事管理制度の中でのコンピテンシー・モデルの役割(その4)~報酬管理との関係性~
定森 幸生
前回に続いて、経営管理ツールとしての「コンピテンシー」の役割の限界と運用上の注意点を検証する際の視点を採り上げます。今回は(4)「報酬管理との関係性」を考えてみます。
(4)コンピテンシー・モデルと報酬管理との関係性
人事制度は様々な施策から成り立っています。中でも、給与やボーナスを算定する報酬管理施策は、経営管理者にとっても一般社員にとっても、最も関心が高い施策でしょう。そのため、会社が人事制度を改訂する場合、報酬とは直接の関係がない施策を改訂したり新規に導入する際でも、往々にしてその施策を報酬管理施策と直接リンクさせようとする例が多くみられます。極端な場合は、「人事制度」イコール「給与制度」との誤解によって、給与や諸手当の算定に直接リンクしない施策は中途半端な施策であると結論付ける例も少なからず見受けられます。
その結果、コンピテンシー・モデルのような新しい人事管理施策が海外から紹介されると、その施策の本質的な目的と、施策導入後の会社業績へのインパクトを精査しないまま、その施策に含まれる手法や運用ツールを何とか数値化して給与やボーナスの金額の算定プロセスを構築することに多大なエネルギーを費やすことになりがちです。
過去には、「年功給与」は、会社業績に関係なく社員の年齢が上がるたびに会社の総人件費負担が重くなる(人件費の下方硬直性)ため、給与の算定に当たって「年功主義」から「能力主義」がもて囃され、さまざまな「能力」を報酬決定のための評価基準に採用した時期がありました。極端な例では、「英語力」も仕事に役立つ「能力」のひとつと認識し、英語のテスト・スコアで一定以上をクリアすると「語学手当」を支給する企業さえありました。
しばらくすると、そのような企業の中には、「能力」だけでは必ずしも企業業績に貢献するとは限らないとの理由で、「能力」に対して報酬を払うのではなく、あくまで達成した「業績の大きさ」に対して支払う「成果給制度」に切り替える方が合理的であるとの判断に基づいて、給与体系を改訂する例が多くみられました。しかし、第5回の「成果主義の本質を正しく認識する」で説明した通り、「成果給(pay for performance)」を導入した企業の中には、成果主義の人事制度に変更しても、給与制度を改訂しただけでは期待したほど業績への顕著な貢献度が見られず、社員のモチベーション維持も難しいことを認識する企業が少なからず生じるようになりました。
その結果、「成果給制度」を導入した企業の中には、あらためて、「成果給制度」導入前に社員に対する報酬の算定方法として使った「能力」の本質を原点に立ち返って見直そうとする企業が増えています。多くの企業に共通する見直しのポイントは、漠然と列挙した「能力」や「技能」を、①「保有能力」(身に付けている能力のうち、現在の業務を遂行する過程で殆ど発揮することのない潜在能力)と②「顕在能力」(現在の業務を遂行する過程で頻繁に、あるいは重要な局面で発揮する職務行動・能力)に大別して、顕在能力について評価のウエイトを大きく位置づけることにあります。
この見直しのポイントは、これまでに説明してきたコンピテンシー・モデルと基本的に共通する点が多いことが分かります。その意味で、コンピテンシー・モデルを報酬算定の基準にしようとする企業が少なからず存在することは、容易に想像がつきます。しかし、コンピテンシー・モデルは、本来、特定の職務に対する成功確率の高さを検証し、その職務への任用・登用または新規採用の基準として活用する手法です。
したがって、経営管理ツールとしてのコンピテンシー・モデルの実効性の高い活用分野は、報酬管理施策よりは企業業績の成果に結びつく社員の職務能力や職務行動を向上させる様々な施策(業務ごとに優先度の高いコンピテンシーの特定、コンピテンシーの具体的な発揮環境・方法・頻度の検証、それらのコンピテンシーの強化を目的としたコーチングや評価面談など)であるべきです。
また、コンピテンシー・モデルは、経営環境や事業戦略の変化によって優先度も変化しますし、これまで潜在能力として発揮されなかった職務行動特性を弾力的に必須のコンピテンシー・モデルと認定する必要が生じることもあります。このような、コンピテンシー・モデル自体の“賞味期限”の短さも、報酬管理ツールとしての実効性の足枷となります。したがって、仮にコンピテンシー・モデルを報酬管理の手法として活用する場合でも、それ以外の報酬要素(compensatory factors)の補完要素として認識することが現実的です。
人事管理制度の究極の目的は、実効性と持続性のある人材を確保し、その業務遂行能力を高めることを通じて、会社の業績向上や経営の持続可能性に対する社員の貢献度を高めることです。その意味では、全社的に最も関心が高い給与やボーナスの算定に関わる報酬管理施策は、会社としてどのような報酬理念のもとで、何を報酬要素の根幹に据え、様々な人事管理諸施策の改廃のたびに報酬要素が大きく変更されることを極力排除することが何より大切なことです。特に、給与制度が数年でコロコロ変わるようでは、社員の制度に対する信頼性が失墜し、制度改定の趣旨や理念をどれだけ懸命に社内に浸透させようとしても、「どうせまた3~4年もすれば制度改定があるのだろうから、それほど真剣に受け止める必要はない」という辛辣な反応(sarcasm)や不信感(distrust)を招くことになります。

-
定森 幸生
Yukio Sadamori

1973年、慶應義塾大学経済学部卒業後、三井物産株式会社に入社。1977年、カナダのMcGill 大学院でMBA取得後、通算約11年間の米国・カナダ滞在を含め約35年間一貫して三井物産のグローバル人材の採用、人材開発、組織・業績管理業務全般を統括する傍ら、日本および北米の政府機関・有力大学・人事労務実務家団体・弁護士協会などの招聘による講演、ワークショップ、諮問委員会などで活躍。『労政時報』はじめ人事労務管理専門誌への寄稿・連載も多数。2012年に三井物産株式会社を退職後、グローバル・プラットフォーム設立。企業や大学の要請で、グローバル人材育成関連のセミナーやコンサルテーションを実施する一方、慶應ビジネススクール、早稲田ビジネススクールで、英語によるグローバル・ビジネスコミュニケーション講座を担当、実務家対象の社会人教育でも活躍中。