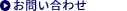グローバル HR ソリューションサイト
by Link and Motivation Group
- グループサイト
-
文字サイズ
2015.04.06
「日本人ビジネスマンの見たアメリカ」No.14 『まず訴える vs. 訴訟は最後の手段』
北原 敬之

グランド・キャニオン(Grand Canyon)はアメリカ合衆国アリゾナ州北部にある峡谷である。コロラド高原がコロラド川の浸食作用によって削り出された地形であり、先カンブリア時代からペルム紀までの地層の重なりを目の当たりにできるところでもある。
アメリカでのビジネスで避けることができないのが「訴訟」です。「訴訟大国アメリカ」などと言われるほど、アメリカでは訴訟が多いです。なぜアメリカは日本より訴訟が多いのでしょうか?1つの理由は、国の成り立ちの違いです。「単一民族・定住型農耕民族・村社会」の日本では、争い事はできるだけしこりを残さないように当事者同士で穏便に話し合いによって解決することが最優先で、「訴訟は最後の手段」と考えられています。それに対して、「多民族・移動型狩猟民族・競争社会」のアメリカでは、第三者による裁判で白黒をはっきりさせることが最も公平な解決方法と考えているため、争い事が起きると、「まず訴える」ことから交渉のプロセスが始まります。弁護士の人数は、日本の3万2千人に対して、アメリカは127万人もいます。訴訟が多いから弁護士が多いのか、弁護士が多いから訴訟が多いのかは、判定が難しいところですが、今回のコラムでは、「訴訟大国アメリカ」について考えてみたいと思います。
筆者のアメリカ駐在時代に、企業の間で話題になった訴訟がありました。訴訟の内容は、「会社主催のクリスマスパーティーで酒を飲んだ社員が、パーティーの帰りに飲酒運転で交通事故を起こし、事故の相手に重傷を負わせた。重傷を負った被害者は、加害者の社員ではなく、飲酒の原因となったクリスマスパーティーを主催した会社を相手に巨額の損害賠償を求めて訴訟を起こした。」というものです。日本人の感覚では、交通事故が起きたのは飲酒運転をした社員個人の問題であって、会社に法的責任はない(道義的な部分は別として)と考えるのが普通だと思いますが、この被害者は「車を運転する可能性があるのにパーティーで酒を用意した会社に責任がある」と主張しました。会社の責任と社員の自己責任の境界線は、判断が大変難しい問題で、法律の専門家でない筆者が軽々に申し上げることはできませんが、1つ言えることは、巨額の損害賠償を求める訴訟の場合、社員ではなくて、支払能力がある(=お金がある)会社を訴えるケースが多いことです。つまり、「誰に責任があるか」は重要ではなく、「誰を訴えたらより多くの賠償金を得られるか」が重要であるということです。
アメリカでビジネスをしていると実に多くの訴訟に遭遇します。PL(製造物責任),知的所有権(特許),人種差別,年齢差別,性差別,セクハラ,パワハラ等々、です。また、クラスアクション(大規模集団訴訟)や懲罰的賠償など日本にはないアメリカ独特の法制度もあります。アメリカで活躍する日本人弁護士など専門家が書いた書籍が多数出ていますので、是非読んで勉強されることをお勧めします。
アメリカに進出して間もない日本企業の場合、訴訟に慣れていないため、いきなり訴えられて過剰反応するケースも少なくありませんが、「アメリカでビジネスをやるには訴訟がつきもの」と割り切って冷静沈着に対処する「強さ」と、状況に臨機応変に対応する「したたかさ」があれば、訴訟を過度に恐れる必要はありません。
筆者の経験でアドバイスできることを以下に記載します。
①日本本社との情報共有
日本企業の場合、アメリカ拠点が訴えられると日本本社がパニックになる例がありますが、そういうことにならないよう、普段から日本本社の法務部門(無ければ担当部門)と情報を共有すること。もっとはっきり言うと、イザと言う時に備えて、トップも含めて日本本社を「慣らしておく」ことが必要です。
②法務問題のウォッチ
有力なローファーム(法律事務所)が発行するニュースレターなどで毎月発生する訴訟のケースをウォッチしておくこと。特に、同業他社と日本企業の訴訟ケースは、自社の訴訟リスクを点検する指標になります。
③信頼できる優秀な弁護士を雇う
アメリカの弁護士は「玉石混交」です。当然腕の良い弁護士は料金(通常は時間でチャージされます)が高いですが、リーガルコストは必要経費と割り切って、優秀な弁護士を使いましょう。日本語のできる日系弁護士は便利ですが、日本語能力と弁護士能力は別ですので、よく見極めてください。
④「法務判断」でなく「経営判断」
訴訟対応では節目節目で決断が求められますが、スピードが重要で、日本本社にお伺いを立てたり、会議で検討している余裕はありません。トップダウンの迅速な決断つまり「経営判断」が必須です。
⑤「勝ち」にこだわらない、「負けない」ことが肝要
「自社は正しいのだから勝って当然」と思う気持ちはわかりますが、「勝ち」にこだわってはいけません。たとえ勝てるとしても、裁判が長期化し莫大な弁護士費用がかかります。「勝ち」でなく「負けない」ことを優先すべきです。アメリカでは、法廷審理まで進む訴訟は5%未満で、訴訟の95%は法廷に行く手前の段階で「和解」等の形で決着すると言われていますが、「白黒ははっきりさせないで和解」という「痛み分け」の形の決着も「会社を守る」という視点で必要です。
訴訟問題は、歴史・風土に起因するアメリカのビジネス文化の一部であり、日本企業のビジネスにも大きな影響を与えるテーマですので、今後もこのコラムで取り上げたいと思います。

-
北原 敬之
Hiroshi Kitahara

- 京都産業大学経営学部教授。1978年早稲田大学商学部卒業、株式会社デンソー入社、デンソー・インターナショナル・アメリカ副社長、デンソー経営企画部担当部長、関東学院大学経済学部客員教授等を経て現職。主な論文に「日系自動車部品サプライヤーの競争力を再考する」「無意識を意識する~日本企業の海外拠点マネジメントにおける思考と行動」等。日本企業のグローバル化、自動車部品産業、異文化マネジメント等に関する講演多数。国際ビジネス研究学会、組織学会、多国籍企業学会、異文化経営学会、産業学会、経営行動科学学会、ビジネスモデル学会会員。