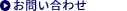グローバル HR ソリューションサイト
by Link and Motivation Group
- グループサイト
-
文字サイズ
2016.09.05
「日本人ビジネスマンの見たアメリカ」No.29 『Equal Opportunity』
北原 敬之

先月開催されたリオデジャネイロ・オリンピックでは、いろいろな競技で日本選手のすばらしい成績や感動的なシーンが見られ、日本が獲得したメダル数も41個と過去最高を更新したということで、日本人として誇りに思います。一方、アメリカの獲得メダル数はダントツ世界1位の121個で、日本の約3倍です。オリンピックの度に思うのですが、なぜアメリカはいつもオリンピックで世界最強なのでしょうか? 日本人と比較すると、相対的にアメリカ人の体格が勝っていることや、抜群の身体運動能力を持つアフリカ系アメリカ人の存在、恵まれた競技施設や練習環境など、いくつかの理由がありますが、もう1つ、筆者は、日本とアメリカの「人材育成」の考え方の違い、特に、その根底にある「Equal Opportunity」の概念の違いが大きいのではないか思います。「Equal Opportunity」は「機会均等」と訳されますが、日本とアメリカではその捉え方が異なっているように感じます。今回のコラムでは、「Equal Opportunity」という言葉について考えてみたいと思います。
「Equal Opportunity」の捉え方のアメリカと日本の違いを一言で言うと、アメリカは「Opportunity(機会)」の方に力点があり、日本は「Equal(均等)」の方に力点があるということだと思います。筆者のアメリカ駐在時代の経験でも、娘が小学校2年生の時、数学(算数)の時間になると、娘のクラスの生徒は、3年生の教室で授業を受ける生徒と2年生の教室で授業を受ける生徒の2つのグループに分けられていたことを思い出します。数学のように生徒によって個人差の大きい科目については、小学校低学年の段階から、能力別のクラス編成によって、「進んでいる生徒」は「もっと進ませる」、 「出来る生徒」は「もっと出来るようにする」指導が行われていました。つまり、「その時点の能力に見合う最適な環境が用意される」ことが「機会」であり、この「機会」は誰でも平等に与えられるべきだ。というのが、アメリカの「機会均等」の基本的な考え方です。「能力別クラス編成」だけでなく、能力と成績によって年齢に関係なく進級や大学進学が認められる「飛び級」、貧しい家庭の子弟でも成績優秀であればトップクラスの大学に進学できる充実した「奨学金制度」もあります。スポーツの分野でも同様で、才能のあるアスリートには年齢に関係なくハイレベルな指導や練習環境が与えられる「スポーツ奨学金」などが用意されています。アカデミズムの世界でも、日本では「助教→講師→准教授→教授」と段階的に昇進していくのに対して、アメリカでは、大学院を修了していきなり教授になるケースもあり、若い人材がいろいろな分野で活躍しています。これらは、すべて、「伸びる人材には更に伸びる機会を与えるべきだ」というアメリカの文化を反映したシステムです。
日本はどうでしょうか。「定住型稲作文化村社会」の日本では、教育でもスポーツでも、集団全体のレベルを上げることが最大の目的であるため、よく言えば「集団主義」、悪く言えば「悪平等」で、能力や進度に関係なく全員に同じ環境を用意することが「機会均等」であるという考え方です。学校を例に言えば、全員に同じ指導をするため、必然的に、平均的レベルの生徒に合わせた指導になるため、平均以上の生徒から見ると「物足りない」、平均以下の生徒から見ると「ついていけない」ということになってしまいます。このシステムは、確かに、全体の平均レベルを上げるには適していますが、レベルの高い人材は「更に高いレベルに挑戦する機会」に恵まれません。「機会」よりも「均等」に力点がある日本のシステムの弱点だと思います。
ここまで教育やスポーツを例に説明してきましたが、実は企業における人材育成についても同様の弱点を抱えています。日本企業の人材育成は、「階層別研修」と呼ばれるやり方が主流で、入社年が同じ社員(いわゆる同期)を1つのグループとみなし、入社後の年数に応じて、グループ全員に同じ研修プログラムを受けさせるというシステムです。前述の学校教育とまったく同じで、全体の平均レベルを上げるには適していますが、レベルの高い人材は「更に高いレベルに挑戦する機会」に恵まれません。日本企業の強みである「集団主義」を否定するつもりはありませんが、人材育成については、集団主義を前提とした「階層別」の伝統から卒業し、個々の人材の能力やキャリアプランに基づいた多様な研修の「機会」を用意するシステムに転換することが求められていると思います。
日本は、オリンピックのメダル獲得数だけでなく、ノーベル賞の受賞者数や大学の世界ランキングなどでも、いつもアメリカの後塵を拝しています。アメリカに勝つには、日本も、「伸びる人材には更に伸びる機会を与える」というアメリカ型の「機会均等」の考え方を取り入れていくべきではないでしょうjか。

-
北原 敬之
Hiroshi Kitahara

- 京都産業大学経営学部教授。1978年早稲田大学商学部卒業、株式会社デンソー入社、デンソー・インターナショナル・アメリカ副社長、デンソー経営企画部担当部長、関東学院大学経済学部客員教授等を経て現職。主な論文に「日系自動車部品サプライヤーの競争力を再考する」「無意識を意識する~日本企業の海外拠点マネジメントにおける思考と行動」等。日本企業のグローバル化、自動車部品産業、異文化マネジメント等に関する講演多数。国際ビジネス研究学会、組織学会、多国籍企業学会、異文化経営学会、産業学会、経営行動科学学会、ビジネスモデル学会会員。