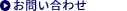グローバル HR ソリューションサイト
by Link and Motivation Group
- グループサイト
-
文字サイズ
2016.09.12
Why Repatriation Matters (Part One)
ガレス・モンティース
In 2010, I entered a doctoral program at the University of Manchester so that I could study and research the impact of globalization on Japanese business people and HR systems. Five years later, I was awarded my doctorate based on a thesis that investigated repatriation and Japanese human resource management (HRM). In this series of articles, I will share in bite-sized pieces some of my observations and conclusions. After all, it is hardly fair to ask anyone other than my supervisor, examiners, and (long-suffering) mother to read the entire thesis.
Why did I become interested in this topic, and why do I think that you might be? Every year, the number of business people who have worked overseas and returned to their home country grows larger. It is highly likely that you know at least one of their number. These people can be referred to as “repatriates,” as opposed to “expatriates,” which is what they were when they went overseas to work, or “inpatriates,” the label given to people brought from other countries to work in a headquarters.
It seems intuitive that of these three processes (repatriation, expatriation, and inpatriation), repatriation would be the easiest to handle. After all, a repatriate is returning to her own country. Unlike when she was an expatriate, she does not have to deal with the potential challenges of an unfamiliar language or unknown business practices. An inpatriate, of course, faces similar hurdles to those of an expatriate, including dealing with strange food, new customs, and a different climate.
Surely, then, repatriation is relatively simple? As it turns out, this is not the case. In 1945, Alfred Schütz described the gap between the person going back and the people who greet him: “In the beginning it is not only the homeland that shows to the homecomer an unaccustomed face. The homecomer appears equally strange to those who expect him, and the thick air about him will keep him unknown” (quoted from “The Homecomer” in the American Journal of Sociology, volume 50, issue 5, pages 369-76).
Alfred Schütz is not alone in noticing the unexpected difficulties of repatriation. Nancy Adler, professor of Organizational Behavior at McGill University in Canada, is perhaps the most famous in a long line of academics to have written on the topic. Repatriates themselves underestimate the challenges, as do their families, friends, and employers. More money is spent by companies on an employee’s expatriation than on repatriation, for instance (see Mark Bolino, “Expatriate assignments and intra-organizational career success: implications for individuals and organizations” in the Journal of International Business Studies, volume 38, pages 819-35). Academic research, too, has tended to focus more on expatriation than repatriation, but there is a growing awareness that repatriates are important for the future success of companies.
Let’s think about that statement for a while: “repatriates are important for the future success of companies.” This makes more sense if we consider why they were sent overseas in the first place. One reason is that it is more practical or cheaper to send someone from the home country to fill a position than it is to try to hire locally. Another is that the expatriate may be expected to teach skills and knowledge to local colleagues, often with a view to handing over to those colleagues at the end of the assignment. Those skills and knowledge may be technical, or they may relate to a common corporate culture. Thirdly, a company may wish to improve communication between different parts of the global organization. Next, the headquarters may hope to gain control over a local company, or at the very least, to observe what is being done. A fifth reason is to develop talented people from the headquarters by giving them overseas experience.
Clearly, these may all apply at the same time. In other words, your president, division manager, or HR department may decide that it is cheaper or easier to send someone from the headquarters than to hire locally. While the expatriate is there, she can pass on her technical and organizational knowledge, and create a healthy flow of information between the local company and the HQ. She can exercise a degree of control over local management, and she can also learn valuable management skills herself. While her salary and various expatriate allowances mean that she is likely to cost the headquarters a lot of money, the benefits listed here show that it may well make sense to send her.
Now let’s imagine what might happen when that person returns. She has likely developed a personal network with key people overseas. She has learned about how to work outside her home country, and she has acquired new technical skills. All in all, she has valuable knowledge. If her company wants to expand regionally or globally, she has the potential to contribute in a positive way. She can assist colleagues in the headquarters who lack similar experience, she can connect those colleagues with people she knows overseas, she can work to solve problems in communication and management arising from working across cultures, and she can collaborate with other repatriates to establish powerful communities and bodies of practice.
Despite all of this exciting potential, many companies fail to manage repatriates and repatriation in anything even approaching an optimal manner. Most academics and practitioners agree that turnover rates are higher for repatriates than for those who do not go abroad. Even if they do not leave, there is evidence that some become frustrated and disillusioned in their jobs back in their home country, not least because they feel their skills are not being used.
Since our clients at LGS are all at various stages of globalizing, my doctoral work has implications and potential that might be helpful. In particular, I have focused on the impact that repatriates have on their home organizations and vice-versa. This is particularly relevant in the light of ongoing speculation about changes in Japanese human resource management practices. As companies become more global, it is reasonable to expect that they will make adjustments that mean they give up some of their original practices. Is that really the case, however? That is one of the key questions that I will address in this series of articles. I hope that you enjoy what follows from now, and I thank you for taking the time to read this far.
2016.09.12
帰任者が何故重要なのか Article 1
ガレス・モンティース
私はグローバル化が日本のビジネスパーソンや人事システムにどのような影響があるのかを研究するために2010年、マンチェスター大学の博士課程に入学しました。5年後、 海外赴任からの帰任者と日本の人事・人材マネージメントを調査した博士論文で博士号を取得しました。このシリーズではその時の所見や、調査の結果をみなさんに少しご紹介したいと思います。私の大学の指導教官、試験官、あとは(なが〜い間、論文に散々協力させられて苦しめられた)母以外に膨大なページ数に及ぶ論文を読んでくださいというわけにはいきませんからね。
まずは何故私がこのトピックに興味を持ったのか、そして何故みなさんにも興味深いのではと考えたかをお話ししましょう。海外赴任を終えて自国に戻るビジネスパーソンの数は年々増えてきています。みなさんのお知り合いの中にも赴任先から戻られたという方がお一人くらいはいらっしゃるのではないでしょうか?そういった方々を帰任者と呼んでいます。英語では海外への赴任者を”expatriates”と呼ぶのに対し、帰任者を“repatriates”と呼び、海外の子会社から本社に赴任してきた人を“inpatriates”と呼びます。( 聞きなれない言葉かもしれませんが“ex-“ は ”〜から外へ”,“re-“ は“再び”,“in_”は”中へ”の意味を持っていますので何故こう言った呼び名なのかなんとなくわかっていただけるかと思います。)
直感的に考えて、これら三つ(海外赴任からの帰任、海外赴任、海外子会社から本社への赴任)のうち海外赴任から帰任するのが一番簡単なような気がします。帰任は結局自分の国に帰るわけですからね。海外赴任に比べたら慣れない言語や商習慣といった壁に当たることもないわけです。海外子会社から本社へ赴任した人もおかしな食べ物、新しい習慣、気候といった同様の困難に対処しなくてはならないのです。
そう考えると、帰任は比較的単純なことのはずでしょう。ところが、調査してみると実はそうではなかったことが分かったのです。1945年、社会学者、アルフレッド・シュッツは帰郷する人とそれを迎える人の間にあるギャップについて記しています。“帰郷した当初は、帰郷した人が見慣れない顔に直面するだけでなく、実は迎える側にとっても同様に帰郷者が見知らぬ人のように見えるのです。帰郷する人に対する期待が彼を見知らぬ人にしてしまっているのです。”(“The Homecomer” アメリカンジャーナルオブソシオロジー volume 50, issue 5, P369~76)
帰郷(帰任)の予期せぬ難しさを記したのはアルフレッド・シュッツだけではありません。 カナダのマックギル大学で組織行動学を専門とするナンシー・アドラー教授がおそらくこの分野では最も有名な論文を発表していると言えるでしょう。帰任者は帰任に対する難しさを過小評価しているのです。これは帰任者だけでなく、その家族、友人、そして彼らの勤める会社にも言えることです。一例を挙げると、会社は帰任者よりも海外赴任者に多くのお金をかけているところからもわかるでしょう。(マーク・ボリノ, “Expatriate assignments and intra-organizational career success: implications for individuals and organizations” ジャーナルオブインターナショナルビジネススタディーズ, volume 38, pages 819-35参照). この分野における学術研究も海外赴任者に注目したものが多くなっていますが、最近では企業の将来的な成功における帰任者の重要性に対する認識も高まってきています。
それでは以下の文についてちょっと考えてみましょう。 “帰任者は企業の将来的成功にとって重要である” そもそも何故会社が後々帰任者となる人々を海外に送り出したかを考えたら、この文章は道理にかなっているのではないでしょうか。本国より必要な人材を送る方が、現地の人を雇うよりも、現実的かつコストも低く抑えられるのは一つの理由でしょう。また海外赴任者に技術や知識を現地の人に教えて、現地の人材を育て、赴任が終わるまでには現地の人に赴任者がしていた仕事を任せられるようにして欲しいという期待もあるでしょう。こう言ったスキルは技術的、専門的な場合もあるでしょうし、企業の共通した文化に関連したものかもしれません。3つ目として、会社はグローバル組織の様々な部分におけるコミュニケーションの円滑化を赴任者に期待しているのかもしれません。そして本社は海外子会社をより上手にコントロールしたいのかもしれませんし、少なくとも状況をよりよく把握することを望んでいることでしょう。5番目の理由として本社で能力のある人に海外経験を積ませより成長させたいという思いがあるのではないでしょうか。
明らかに、これら5つ全てを目指している場合もあるでしょう。言い換えれば、社長、部門長、人事部 は現地で人を雇うよりも本社から人を送り込むほうがコストが抑えられる、または容易だと考え赴任者を送りこみ、一方で赴任者には赴任中に技術や知識を現地の人に教え、かつ本社と海外子会社のスムーズな情報伝達基盤を構築し、現地の経営をある程度管理し、そして赴任者自身も貴重な経営技術を学ぶことを期待しているのです。赴任者には給料に加え様々な手当が支払われますので、会社にとっては大きな費用がかかりますが、それでもここに並べた利益を考えると海外赴任者を送るのは理にかなったことになるのです。
では赴任者が帰任した後のことを考えてみましょう。帰任者は海外赴任中に海外で重要な人々との人脈を構築してきたに違いありません。自国以外で働くことを学び、新たな技術を習得してきたことでしょう。概して言えばとても貴重な知識を持っているのです。会社が地域で、若しくはグローバルに成長したければ、帰任者は大いに会社に貢献できる可能性を秘めているのです。例えば、赴任中に構築した人脈を使って、海外経験のない本社の同僚と海外の社員の橋渡しをしたり、異なった文化圏でのコミュニケーションや経営に関係した問題解決に一役かったりすることができるかもしれません。また、帰任者同士で経験や知識を共有し、協力して会社に貢献するということも考えられます。
ところが、こういった素晴らしい可能性にもかかわらず、多くの企業が帰任の扱いを間違い、帰任者の育成や活用ができていないのが現状です。学術研究だけでなく現場の人々も、帰任者の離職率が、海外に赴任したことのない人々よりも高いと言っています。また離職こそしないけれども、自国での仕事に不満を感じたり、幻滅したり、とりわけ、せっかく培った経験や技術を使いきれていないと感じている帰任者がいることも確かです。
LGSのお客様はグローバル化の様々な過程にいらっしゃいますので、帰任者が自国の組織に与える影響や、その逆に自国の組織が帰任者に与える影響に重点を置いた私の博士課程での研究が、特に役に立つのではないかと思います。 昨今、日本の人事・人材マネージメントが変化してきていると言われ続けていますので、それらとの関連性も高いと認識しています。企業のグローバル化が進むにつれ企業内でも様々な調整や変化が必要となり、今までと同じやり方は続けられなくなると考えるのももっともでしょう。でも本当にそうでしょうか?これまでのやり方を切り捨てたり、変更したりしているのでしょうか? これが今後このシリーズを通して、取り組んでいきたい疑問の一つです。 6回の短いシリーズではありますが、皆様が面白いと思って読んでくださったら幸いです。ここまで読んでくださってありがとうございました。

-
ガレス・モンティース
Gareth Monteath

- ケンブリッジ大学 経営学修士(MBA:最優秀論文賞)。シェフィールド大学 中国学修士(MSc)。2016年、マンチェスター大学にて、経営学博士課程(DBA)を修了し博士号を取得。ロンドンのダイワ・ヨーロッパに勤務後、1991年にJET プログラムで来日以来、20年超の日本在住、勤務経験を誇る。1994年に前身の株式会社インテック・ジャパン現・株式会社インテックに入社。現在は株式会社リンクグローバルソリューションの執行役員の立場で、プログラムディレクターとして研修の企画・立案、および外国人講師の育成を担う。自らも日・英両言語を操りトップインストラクター、ファシリテーターとして年間100日以上登壇。ジェトロ主催のビジネス日本語能力テスト1級。著書「WIN-WIN 交渉術」(共著、清流出版)など。