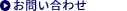グローバル HR ソリューションサイト
by Link and Motivation Group
- グループサイト
-
文字サイズ
2015.01.19
【世界最北の日本レストラン―フィンランドで苦闘した あるビジネスマンの物語(50)】蜘蛛の糸
長井 一俊

皆が作ってくれたクリスマスツリー
パブでの乱闘に巻き込まれた結果、ぐらぐらになってしまった一本の奥歯は、お医者様の治療のかいも無く、数日後の夜更けに抜け落ちてしまった。日本から送られて来た、大好物のゲンコツ煎餅を寝酒の肴にしたのが致命的だった。
「下の歯が抜けたら屋根に投げろ」と日本では言われるが、雪の降る深夜にいったいどうしたら良いものか、と私はいつもテーブル代りに使う、キッチンの出窓の前で思案していた。その時、出窓に沿って吊るされている白いカーテンの最下部をゆっくりと動く、黒っぽい小さな点が見えた。目を近づけると、ネズミ色をした小さな一匹の蜘蛛であった。
日本では夜の蜘蛛は泥棒を呼ぶと言われ、不吉なものとされている。ましてや、歯が抜けてしまった直後である。本来の私なら、ティシューで潰して、ゴミ箱に投げ捨てるところだ。しかし極寒の夜、この大きな家の中で生きているものは、自分と一匹のハエだけだと思っていた私は、その他にも生命体が存在していた事に驚かされた。そして同時に、芥川の「蜘蛛の糸」を想い出した。
生涯に一度だけ「一匹の蜘蛛を助けた」という極悪人の善行をお想い出したお釈迦様は、蜘蛛の糸で彼を地獄池から天国に引き揚げようとした逸話だ。
冬になり人通りの絶えたポリの街で、私のレストランへ来る客は固定客のみに激減し、経営は夜のパブに来る酔客で辛くもなりたっている。いろいろ言い繕ってはみても、今の私はオーナーシェフではなく、呑兵衛の居酒屋のおやじでしかない。到底天国には行けそうにない。しかし、この蜘蛛さえ助ければ、天国に行けるかもしれない、と考えた。
私は、そっと右手の中指を蜘蛛の前に近づけてみた。数秒後、蜘蛛は私の指に乗り移ってきた。私を味方だと判断したのだろう。そして、ゆっくりと手の平に向かって這い寄ってきた。手の平の窪みでしばらく散歩した後、又ゆっくりと中指を伝ってカーテンに向かった。去って行く蜘蛛に小さな声で『ありがとう、又来いよ』と話しかけた。私の言葉を受けてか、蜘蛛は中指の先端でしばらく佇み、そしてゆっくりとカーテンに戻って行った。その間私は、蜘蛛と人間は心が通じ合うのだ、と確信した。だからこそお釈迦様は数多の生物の中から蜘蛛をもって人を救おうとしたのだ。
私は家内に、この蜘蛛の話をメールで伝えた。すると、「ハエの次は蜘蛛ですか!猫も飼えないのなら、クリスマスツリーでも飾って、鬱を晴らしてはいかがですか?」との返事が戻ってきた。
なるほど…。私はまず樅の木の入手方法を考えてみた。置く場所はリビングが良い。しかしそこは、かつて幼稚園の集会場であっただけに、非常に広く天井も高い。よってクリスマスツリーは大きくなくてはならない。しかし、私の車では大きな木は運べない。
翌日、建築会社を経営するアンティ君に電話をした。すぐに、彼はピックアップ・トラックにノコギリを積んでやってきた。森の多くは国有林で、無断で木を切ることは禁じられているのだが、小さな間伐材を切るのは、森の繁茂を防ぐ効果があるので、大目に見られている。
次の問題は飾り付けだ。翌日常連客の女性に相談してみた。彼女は『私に任せて』と言って、携帯でメールを打ち始めた。
店が休みの翌月曜日、大勢の女性達がいろいろな飾りを持って家にやってきて、アッと言う間に立派なクリスマスツリーが出来上がった。私の子供の時代のクリスマスツリーといえば、金や銀紙で出来た星、赤と緑のセロファンから作られたモール、それにピンポン球の大きさのガラス玉だった。しかし今では、夏みかんほどの大きさの色とりどりのグラスボールやLED電球がフンダンに使われている。
リビングは一度に明るくなり、私の心も華やいできた。北欧人にとって、クリスマスツリーは、寒くて暗い冬をやりすごす重要な手段である事を改めて知らされた。
深夜に店から帰ると、玄関でいつものように一匹のハエが出迎えてくれて、そしてリビングではタイマーでセットされたクリスマスツリーが私の帰りを待っていてくれる。グラスにブランデーを満たしてから、半時程ツリーの前のソファーに座る。数色のLEDが放つ光が、色とりどりのグラスボールに反射されて、光のシャワーとなって私を包んでくれる。それ迄とは全く違う幸せな夜を過ごせるようになった。ブランデーグラスを揺らすと琥珀色の水面がキラキラと光を放つ。その光の一粒一粒からポリの人たちの友愛や、イエス様の慈悲が感じられる。
お釈迦様がイエス様に依頼して、あの小さな蜘蛛を差し向けられて、北欧の厳寒を乗り切れるように私を励まされたに違いなかった。

-
長井 一俊
Kazutoshi Nagai

- 慶応義塾大学法学部政治学科卒。米国留学後、船による半年間世界一周の旅を経験。カデリウス株式会社・ストックホルム本社に勤務。帰国後、企画会社・株式会社JPAを設立し、世界初の商業用ロボット(ミスター・ランダム)、清酒若貴、ノートPC用キャリングケース(ダイナバッグ)等、数々のヒット商品を企画・開発。バブル経済崩壊を機にフィンランドに会社の拠点を移し、電子部品、皮革等の輸出入を行う。趣味の日本料理を生かして、世界最北の寿司店を開業。