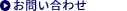グローバル HR ソリューションサイト
by Link and Motivation Group
- グループサイト
-
文字サイズ
2016.02.22
【世界最北の日本レストラン―フィンランドで苦闘した あるビジネスマンの物語(64)】神秘なる日本語
長井 一俊

氷結したコケマキ河上流
2月も下旬になると、ポリの町は1年で一番寒い日を迎える。明け方零下20度まで冷える日も珍しく無く、昼になって零下5度に上がると暖かくさえ感じられる。人の感覚はすべからく相対的であるらしい。
私の好きな短歌に、江戸末期の歌人・橘曙覧(たちばなあけみ)が詠んだ
“楽しきは たまに魚煮て 子供らが うましうましと 言ひて食ふとき”
がある。

コケマキ河に合流する支流
この歌からは、人間の二つの感覚について相対的である事が読み取れる。一つは、幸福に関する感覚である。貧しい暮らしをしていると、子供の笑顔だけで幸せを感じられる。二つ目は、味覚である。ハンバーグで育った現代の子供達には、煮魚の美味しさはなかなか分かってもらえない。
北欧の清涼な夏も美しいが、北欧らしい本当の美しさが見られるのはこの時期だ。所用があって、コケマキ河上流に住む友人を訪ねたが、内陸に進むにつれて寒さは厳しさを増し、支流や小川がこの大河に流れ込む地点(添付写真)では、凄まじくも美しい光景と出会った。芭蕉や蕪村がこの光景をみたら、どんな俳句を詠んだであろうか。
私はルールにうるさい俳句は苦手で、何でもありの川柳しかやらない。俳句はもっぱら自然を、川柳は世間を詠むのだが、この光景を見て俳句を勉強しなかった事が悔やまれた。
熊や鹿たちは、この絶景を毎日楽しんでいるのに、人は美しいところには住まず、ごみごみしたところに集まる。それとも、人間が住むと、美は逃げ出してしまうのか。自然美は明らかに文明と反比例している。美が利便性に負けてしまうのは、悲しい限りだ。
日本へ1週間たらずの一時帰国をしてから2ヶ月が経つと言うのに、いまだに日本を発つ早朝のことが忘れられない。ラジオを聞きながら、帰り支度をしていると、ドナルド・キーンによる新古今和歌集の解説が聞こえてきた。新古今和歌集は日本文学の至宝と言われ、解釈はすこぶる難しい。しかし米国人の彼が、日本の誰よりも判りやすく教えてくれた。
先入観を持たずに、純粋に日本語を勉強した外国人だからこそ、外連味の無い、爽やかな解説が出来たに違いない。
幕末から維新にかけて、日本を訪れた西洋人が、一番驚いたことは、荒ぶるサムライが短歌をたしなみ、裏長屋に住む庶民が、俳句や川柳を詠んだ事だという。西洋人のほとんどは、一生に一度たりとも詩を詠む事がない。
来訪者の中でも、英国人バジル・チェンバレン(1850~1935)は日本の文化、特に日本文学に魅せられ、古事記を英訳して出版までした。かの有名なラフカディオ・ハーン(=小泉八雲、1850~1904)は、アメリカに留学中の貴族院議員・服部一三からこの本を贈呈され、日本文化に魅せられて来日し、帰化してしまった。
又、維新にまつわる多くの歴史書や映画に登場する、英国の外交官アーネスト・サトー(1843~1929)は通訳官として、日本の文明開化に大いに貢献した。チェンバレン、ハーン、サトーは三大日本学者と呼ばれているが、三人の共通点は、神秘主義者であったことだ。彼等語学の天才たちには、日本語が大いに神秘的に映ったようだ。
そのハーンは、「川柳は言葉の手品である」と述べている。ドイツの哲学者ニーチェは短い文書で、ドキッとするような名言を沢山残している。例えば「真実などは無い。あるのはその解釈だけだ」「人は愛と革命のために生まれた。」「愛の終着は、善悪では計れない」等々。しかし、これらの原文を見て、アルファベットを数えてみると,どれも数十文字を消費している。それにくらべると、日本語はすごい。芭蕉の句、 「荒海や 佐渡によこたふ 天の川」 は、たった17文字で宇宙さえ飲み込んでしまった。
実は、昨年の9月に載せた私のコラム(59号 別れの秋)の末尾で書いた、私が兎を抱かなかった理由を、 「手に取るな やはり野に置け 蓮華草」 の句にかこつけたが、これに対して古い仲間からクレームが入った。「この句の作者・滝野瓢水を、俳人にして奇人、と紹介している以上は、句の裏の意味も解説すべきではないか」とお叱りをうけた。
句の主役「蓮華草」は、実は瓢水が入れ込んだ女郎の源氏名であった。彼は彼女本人や周囲の人達に“近いうちに蓮華草を水揚げする”と公言してしまった。ところが、懐具合が悪く、水揚げどころではない。そこで、この美しげな句を詠んで、世間を煙にまいてしまったのである。まさに手品に他ならない。
残念ながらフィンランド語をマスターしていない私は、彼等の誇る叙事詩「カレワラ」を読むことが出来ないばかりか、日常交わされる冗談や駄洒落も理解するに至っていない。
英語でなら文章もジョークも多少は理解出来る。英米人も言葉の遊びは好きだ。私は昔、クラスメートから、“CAN CAN CAN CAN.”の意味がわかりますか?と質問されたことがある。子犬が吠えているのではない。その答えは「缶屋さんはブリキを缶に出来る」だそうだ。ブリキはtinであるが、この際はcanでも良いようだ。
しかし、言葉の遊びでは日本語は傑出している。日本の狂歌に、 うりうりが うりうりにきて うりのこし、うりうりかえる うりうりのこえ(瓜売が、瓜、売りに来て、売り残し、売り売り帰る、瓜売の声)がある。他の言語では到底競えない。
多くの言語に精通するキーンは、著書「日本語の美」の中で、漢字と音標文字を混用する日本語がおそらく世界で一番難しい言語だろう、と述べている。
そして、世界中の主な言葉のほとんどがpre position (前位置)語であるのに対して、フィンランド語と日本語はpost position (後位置)語であり、語尾の変化によって状況を伝達している。このことが、外国人に対して難しさを倍加している。
私は何度か、欧米の自治体から頼まれて、市民に日本語を教えた事がある。日本語には、文法等は在って無きが如くで、ほとんどが慣用語にこなれてしまっている。私がやれた事と言えば、日常多用される言葉を丸暗記させることだけだった。これでは教えたことにならない。日本語の難しさに気づいたのは、この時だった。
日本語は難しいだけではなく、美しさも格別である。日本の叙情詩を、解説したり、意味を教える事は出来ても、外国語に言い換える事は不可能である。
平家物語の冒頭 “祇園精舎の鐘の声、諸行無情の響き有り”の美しさを他の言語に直訳する事は出来ようか。日本酒の美味さを、小麦粉で再現する事が出来ないのと同じだ。
他方、ヴェルレーヌの書いた「秋の歌(落葉)」を上田敏は「海潮音」で、
“秋の日のビヨロンのためいき ひたぶるに身にしみて うら悲し”
と原文より遥かに少ない文字数で、情緒を見事に再現している。まさに日本語は神秘である。
今、日本では少子化が加速し、人口の半減もさして遠い日の話ではない。その結果予想される経済の縮小は、生産性の向上で補えるかもしれない。しかし、この美しい言語を使う人の数は、まぎれも無く減ってしまう。これを救うには北欧諸国のように、子供の数により手当を累進的に増す政策を施すしか、術が無かろう。
“台所が苦しいから、もう一人こさえましょうよ”となる。

-
長井 一俊
Kazutoshi Nagai

- 慶応義塾大学法学部政治学科卒。米国留学後、船による半年間世界一周の旅を経験。カデリウス株式会社・ストックホルム本社に勤務。帰国後、企画会社・株式会社JPAを設立し、世界初の商業用ロボット(ミスター・ランダム)、清酒若貴、ノートPC用キャリングケース(ダイナバッグ)等、数々のヒット商品を企画・開発。バブル経済崩壊を機にフィンランドに会社の拠点を移し、電子部品、皮革等の輸出入を行う。趣味の日本料理を生かして、世界最北の寿司店を開業。