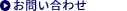グローバル HR ソリューションサイト
by Link and Motivation Group
- グループサイト
-
文字サイズ
2015.09.07
【グローバル人事管理の眼と心(8)】成果を挙げ続ける人材集団を構築する条件(その3)
定森 幸生
<「歴史観」に基づく教訓>
ビスマルク(Otto von Bismarck)の言葉に、「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」というものがあります。挑発的なトーンなのでよく引用されますが、もともとは、Only a fool learns from his own mistakes. The wise man learns from the mistakes of others. (自分自身の失敗から学ぶことには限界があるので、先達の失敗も教訓にせよ。)という趣旨です。海外拠点の人材マネジメントについても当を得た箴言と言えるでしょう。これまで日本企業が海外事業展開の過程で遭遇してきた国際人事マネジメントに関する多くの教訓の中から、特に重要な4つの「歴史の教訓」を、今回と次回に分けて指摘しておきます。
―歴史の教訓① ローテーションの狭間で失われる継続性―
本来、会社の人事管理のあり方や制度運用の成果は、企業規模や業種にもよりますが、通常10年程度の時間軸で検証し、次の10年に向けての改善を志向すべきものです。しかし、現実には、人事管理に携わる社員もライン管理を担う社員も、数年のローテーションで異動することが多い日本企業にとって、どうしても目先の実務上の問題解決に追われたり、変化への対応を急ぐプレッシャーのあまり、時流に乗った話題性のある人事管理手法の導入や新しい人事施策の企画立案それ自体が目的化される傾向があります。
海外拠点の人事管理となると、現地事情が皮膚感覚でリアルタイムに日本本社に伝わりにくいため、どうしても現地のライン管理者任せになり、数年のローテーションで現地を離れる経営幹部や管理職の個人的裁量に委ねられるケースが多くなります。その結果、組織運営や人事制度の運用に関する会社方針の一貫性、整合性、継続性が失われるリスクに晒されるのです。人材マネジメントにおける会社と個人の“テンポ”の乱れで不協和音がおきると、優秀な人材を失ったり、在籍するホスト国社員のモラールの低下を招くことになります。
経営幹部の人事異動を契機に、マンネリを打破したり、長年の悪癖や制度の陳腐化を改めることは必要ですが、海外拠点の経営幹部が変わったからと言って、現行制度の実態を十分理解しないまま頻繁に人事制度を変えようとすると、現行制度だけでなく新制度に対するホスト国社員の信頼まで失うことになります。なぜなら、「新制度が導入されても、現在の拠点幹部が異動すれば後任の経営幹部がすぐまた別の制度を作り直すだろうから、制度に振り回され続けるだけではないか」という懐疑的な反応を誘発するリスクが高くなるからです。
人事制度を作り替えること自体は、人事管理関連の人たちを中心とした一部の関係者の一過性の労力と作業コストだけで比較的簡単に達成できます。 しかし、全社レベルで一貫性をもってその制度を効果的に運用し、社員が組織業績の向上に貢献し続けるよう動機付けるためには、その何倍もの労力と時間とその他の間接コストが必要です。ライン管理者とスタッフに対して新制度の意義を周知徹底させ、制度に対する理解と信頼を深めさせるためには、数年間の制度運用の実績に基づいた検証と改善点の精査が不可欠であることを忘れてはなりません。
―歴史の教訓② 本質(substance)と形式(style)の見分け―
人事管理の分野には、採用、社員区分・配員、研修・人材開発、昇進・任用管理、給与・福利厚生管理、業績管理・人事考課、労使交渉・法令対策、退職手続など多くの局面において、技術的かつ専門的な知識を必要とする施策や手法が存在します。時には、同じような施策であっても、ネーミングや形式の違いによって、あたかも本質的に異なった施策であると誤解したり、専門用語が一人歩きして、本来の内容から乖離した運用がなされることもあります。
また、著名な企業や業界の代表的な企業が導入した人事制度や諸施策を、導入に至った背景や制度の設計思想や施策の細目を、自社の組織環境に適合するか否かについて十分な検証をしないまま、制度のネーミングやキャッチフレーズに共感しただけで導入するケースも多く見られます。最も端的な例として、本コラム「第5回 成果主義の本質を正しく認識する」で触れたとおり、過去十数年の間に、日本大手企業を中心に、「職能資格制度」は古典的な日本の人事制度であって年功序列の弊害をもたらす時代おくれの制度であるとの事実誤認と、「職務給」こそが欧米的で時代の趨勢であるという根拠のない思い込みによって、両者を対立概念と位置づけ、「職能資格制度」を廃止して「資格給」から「職務給」に舵を切る動きが散見されました。しかし、何年経っても期待どおりには社員の士気も業績貢献度も改善しないため、結局もとの人事制度に戻すことを決める企業が少なくないことも事実です。
「職能資格制度」の本質は、日本的でも欧米的でもありません。強いて言えば、昔も今も、その本質は全世界共通の人事管理手法の“プロトタイプ”なのです。日本の大企業に限らず、例えば、職員数約270万人を擁する米国連邦政府の報酬体系は、一部の幹部ポストを除いた一般職(General Schedule)を 15のグレードに区分し、さらに各グレードについて、経験年数や習熟度に応じて10段階の“Step”が設定されています。また、州による生計費水準の違いを勘案し、全米を34の地域に分けて個別のSalary Tableを作成し、それを毎年の物価変動を反映させて改訂しています。(詳しくは、米国連邦人事管理局のサイトhttps://www.opm.gov/policy-data-oversight/pay-leave/salaries-wages/2015/general-schedule/を参照)どのような仕事でも、真面目に取り組んでいる限り、経験年数に応じて職務能力や習熟度が高まる蓋然性を認識するのは、洋の東西を問わないということです。
日本では、大企業を中心に、経済成長が著しかった過去数十年の間に、「職能資格制度」の運用基準となる報酬要素(compensable factor)を、採用時点で一定の能力・資質をもった人材を職務経験や企業内教育を通じて成長させることを前提に、職能(職務遂行に必要な能力)よりは主に学歴と入社年次・在籍年数に重きをおいて、(1級、2級…のように)グレード化して運用してきただけのことです。「職能資格制度」が年功主義的なのではなく、ユーザー企業が制度を“敢えて”年功主義的色彩を強めて運用してきただけのことです。この点についての正しい“歴史認識”は極めて重要です。
米国企業で多く採用されているとされる「職務給制度」は、報酬要素の主体を職務能力や年功による成熟度の代わりに、それらを必要とする「職責・役割」を基軸にして、社内での相対的な重要度(経済価値やジョブサイズ)に応じてグレード化したものですから、その意味では、職能資格制度の対立概念ではなく、むしろ“同根”と言うべきです。報酬要素による区分(資格、グレード)によって報酬格差を設ける本質的な概念は、日本企業も米国企業(および政府機関)も同じです。因みに、仕事の性格が概ね均質化されているプロフェッショナル・ファーム(会計士事務所、弁護士事務所、コンサルティング会社など)も、当然といえば当然ですが、職能資格制度の有力な“ユーザー”なのです。

-
定森 幸生
Yukio Sadamori

- 1973年、慶應義塾大学経済学部卒業後、三井物産株式会社に入社。1977年、カナダのMcGill 大学院でMBA取得後、通算約11年間の米国・カナダ滞在を含め約35年間一貫して三井物産のグローバル人材の採用、人材開発、組織・業績管理業務全般を統括する傍ら、日本および北米の政府機関・有力大学・人事労務実務家団体・弁護士協会などの招聘による講演、ワークショップ、諮問委員会などで活躍。『労政時報』はじめ人事労務管理専門誌への寄稿・連載も多数。2012年に三井物産株式会社を退職後、グローバル・プラットフォーム設立。企業や大学の要請で、グローバル人材育成関連のセミナーやコンサルテーションを実施する一方、慶應ビジネススクール、早稲田ビジネススクールで、英語によるグローバル・ビジネスコミュニケーション講座を担当、実務家対象の社会人教育でも活躍中。