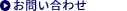グローバル HR ソリューションサイト
by Link and Motivation Group
- グループサイト
-
文字サイズ
2015.11.02
【グローバル人事管理の眼と心(10)】人事制度の基本理念は「特定個人」と「特定多数」
定森 幸生
人事制度とは、社員一人ひとりの職務行動が社業の発展に貢献することを期待して、会社が「特定個人」とその集合体としての「特定多数」の社員を対象に、さまざまな時間軸の中で種々の施策を必要に応じて実行するためのシナリオです。あたかも「不特定多数」の社員、あるいは一律に「全社員」を想定したように思われる施策であっても、基本理念として必ず特定の個人の役割や仕事振りを想定しなければ、“魂の入った”シナリオにはなりません。想定した特定個人の職務行動に直接影響を与えるパワーの源は、会社の社員に対する期待の大きさと支援体制の存在です。それを、人事制度のさまざまな局面で社員が実感できる工夫がなければ、その人事制度は社員のモチベーションを高めるパワーに欠け、存在価値の低い存在となります。
1.業績管理が人事制度の根幹
海外拠点の人事制度を新たに設計したり、現行制度を改訂する際に、最も優先度が高い施策は「業績管理(performance management)」です。業績管理とは、一人ひとりの社員について、概略以下のようなプロセスを経て、確実に仕事の成果をあげられるよう、ライン現場の責任者である上司とその部下が一体となって会社にコミットすることです。
①あらかじめ定義された各社員の仕事(役割)の範囲内で、毎期初に、仕事を通じて達成すべき具体的な目標を、上司と部下が話し合って設定する。何をもって目標を達成したと判断するかも明確に設定する。
②仕事の進捗状況を上司がタイムリーに把握し、目標達成のために部下が継続して実行すべきことや新たに実行すべきこと、さらには上司の立場で部下にどのような支援(accommodation and facilitation)ができるかについて、上司と部下が随時確認しあい、上司の部下に対する業績期待の大きさを部下に実感させることによって、部下にその仕事への強い当事者意識(ownership)を育ませる(⇒モチベーションを高める)。
③期末(中間期末・年度末)に、目標の達成度、仕事の進め方、リスク管理・危機対応、関係部署との協力関係など、定性・定量両面での成果を総括する。
④上記②と③に基づき、年度末に来期以降の仕事(役割)を再定義し、会社の事業戦略に即して目標設定、成果の判定方法などにつき、上司と部下が話しあう。
上記のうち、特に大切なプロセスは②です。①はすべての基本ですが、目標を設定しただけで自然発生的に成果が生まれる訳ではありません。③はあくまで「結果」の評価であって、そこに至るまでのさまざまな外的・内的要因や、特定個人である部下の業務行動を具体的かつリアルタイムで把握・分析しなければ、成果の自然発生を座視しているのと同じです。これでは、上司は管理職としての職務を果たしたことにはなりません。
「成果主義」の人事制度を導入した企業が、期待通りに人事制度が根付かないことに苦悩しているとすれば、その原因は、上記③の結果の評価記号に基づいて(A評価なら10%、B評価なら6%・・・というように)機械的に給与格差をつける事務作業に終始しているからで、それは「成果追求主義」ではなく、むしろ「結果追認主義」とでも言うべきものです。
「成果主義」とは、上司と部下が「めざす成果から、片時も目を離さない+離させない」組織行動に他なりません。したがって②では、会社(上司)が期待する「成果」と社員(部下)の期中業績との間の「距離」をモニターし、与えられた期間(半年または1年)のうちに成果を確実なものにするため、必要に応じて何度でも上司と部下が話し合うことが求められるのです。
その過程で、ホスト国社員が実際の仕事を通じて全社的なグローバル事業戦略、経営計画、ミッションやビジョンなどを、単なるスローガンではなく、ホスト国事業とその担い手である自分自身の役割との関係を通じて、地に足の着いた理解をすることが可能になるのです。その意味では、業績管理は、日本本社でももちろん大切ですが、グローバルな事業展開をする企業の海外拠点での人事制度の中では、際立って重要な人事施策なのです。
2.これからは「異文化コミュニケーション」ではなく「特定個々人との“OJC”」
業績管理の主役は人事担当部署ではなく、事業戦略の実行と成果に責任をもつ各ライン現場の管理者です。日本本社から海外拠点に派遣されるライン管理職の場合は、日本の生活文化、自分の会社の企業文化、個々の業界文化に触れながら仕事を経験した後、新たにホスト国の生活文化や業界文化に直面します。ホスト国社員の業績管理を行う過程でも、いくつもの次元の異なる文化の影響を感じる場面がありますから、多くの文化(=行動原理・規範)をパラメーターとする“高次方程式”を解くような環境に身を置くことになります。
このような環境のもとで、ビジネス実務のプロとして責任ある正しい判断を下すために大切なことは、このコラムの第1回で触れた文化的先入観や固定観念に囚われることなく、多くの文化的パラメーターの中から、特定の個人である部下の職務行動に本当に影響を与える要因が何かについて、個々の職務に関する客観的事実に即して冷静に見極めることです。これまで多くの国の事業所で部下の職務行動を大きく左右する要素を検証した結果、特に注目すべきものとして、自分の職務への精通度や共感度、職務能力への自信の程度、上司を含めた周囲の人たちの理解度や協力の有無、所属部署や社内他部署に対する自分の影響力や彼らの自分に対するリスペクトの程度などが挙げられます。グローバル・ビジネスの現場では、学説や通説で注目される特定の国の生活文化や習慣といった漠然とした要素は意味がありません。特定の組織の中での個別の仕事に関する特定個人の自尊心や向上心に対する正当な評価、自分の努力の結果得られる達成感の大きさなどがモチベーションの源泉なのです。
ホスト国の生活文化に密接に関係する商品やサービスの提供が事業活動の中心である場合でも、皮相的な文化論で片づけないで、冷静な実務家の視点で市場調査を行い、同じホスト国の消費者・生活者の間でも社会的立場の違い、所得・家族構成・生活環境の違いによる消費性向や嗜好の違い、さらには宗教上の理由による行動原理や価値観の違いなどを分析し、それぞれのマーケットセグメントに対してどのような商品やサービスを提供すべきかを、業績評価の過程で徹底的に議論する必要があります。
ホスト国の社会の利益やニーズに最大限貢献しようとするそのような真摯な企業の経営姿勢を、業績評価の過程でホスト国社員と徹底的に話し合うこと(筆者はこれをon the job communication: OJCと呼びます)こそが、これからのグローバル・ビジネスに求められるコミュニケーションの真髄なのです。そして、このアプローチが、最近特に重視されている「ダイバーシティ・マネージメント」の基盤になるのです。

-
定森 幸生
Yukio Sadamori

- 1973年、慶應義塾大学経済学部卒業後、三井物産株式会社に入社。1977年、カナダのMcGill 大学院でMBA取得後、通算約11年間の米国・カナダ滞在を含め約35年間一貫して三井物産のグローバル人材の採用、人材開発、組織・業績管理業務全般を統括する傍ら、日本および北米の政府機関・有力大学・人事労務実務家団体・弁護士協会などの招聘による講演、ワークショップ、諮問委員会などで活躍。『労政時報』はじめ人事労務管理専門誌への寄稿・連載も多数。2012年に三井物産株式会社を退職後、グローバル・プラットフォーム設立。企業や大学の要請で、グローバル人材育成関連のセミナーやコンサルテーションを実施する一方、慶應ビジネススクール、早稲田ビジネススクールで、英語によるグローバル・ビジネスコミュニケーション講座を担当、実務家対象の社会人教育でも活躍中。