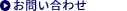グローバル HR ソリューションサイト
by Link and Motivation Group
- グループサイト
-
文字サイズ
2016.12.19
【グローバル人事管理の眼と心(24)】職務能力評価の変遷とコンピテンシー・モデル(その2)~コンピテンシーの源流:マクレランドとボヤティズ
定森 幸生
企業活動におけるコンピテンシーが社会の関心を集めるようになったのは、米国ハーバード大学の心理学者マクレランド教授(David McClelland) が、1973年1月にAmerican Psychologist誌に発表した“Testing for Competence Rather Than for Intelligence” と題する論文で、「人の能力を測定する方法として、それまで学生や社会人の間で広く認知されていた知能テスト(intelligence test) や適性テスト(aptitude test) は、社会人としての仕事や活動 (real life outcomes)での成功確率を占う手段としては信憑性が乏しい」と指摘したことがその発端です。
この論文を発表した後、マクレランドは、米国務省の委託を受けて、若手外交官の選抜方法の有効性の実証研究を行いました。この委託研究の目的は、「トップクラスの大学を卒業し、知能テストや適性テストの成績にも優れた外交官について、在外公館での在勤期間中の業績に格差が生じるのはなぜか?」という米国務省の問題意識に対する答えを出すことでした。マクレランドは、優れた業績を挙げている外交官を対象に、過去の成功体験や事象への取り組み姿勢に焦点を絞った質問 (behavioral event interview: BEIと略されます)を通じて、high performer の間で認められる共通の行動特性を明らかにしたのです。
この調査の結果、①学業成績や知能指数は外交官の業績の高低との間には顕著な相関関係は認めらない、②外交官の職務について成功確率の高い人物には下記3つの特徴的な行動特性(コンピテンス:competence)が認められるとマクレランドは結論付けたのです。
a)異なる生活文化に対する豊かな感受性を発揮し、対人関係を巧みに行う
(cross-cultural interpersonal sensitivity to people from foreign
cultures)
b) どれだけ困難な相手に対しても自制心をもって接し、建設的な人間関係を維持できる
(the ability to maintain positive expectations of others despite provocation)
c) 政治的な人脈を素早く形成できる
(speed in learning political
networks)
(註)American Psychologist誌に掲載された論文では、competency (コンピテンシー)ではなく competence (コンピタンス)が使われましたが、後にマクレランドはじめ多くの心理学者が competency (複数形ではcompetencies)を使うようになり、1990年以降アメリカではcompetencyが定着しています。コンピテンシーの概念が日本の産業界や政府機関に伝わった時点でも、competencyが使われています。
この研究を通してマクレランドが強調したのは、従来の心理学的分析手法によって個人の行動原理に繋がる性格や適性を包括的に抽象化して、その人の性格や適性が顕著に発揮される場面を多くの可能性の中から予測することよりも、現実に特定の仕事やミッションを立派に成し遂げている個人が、具体的な仕事の環境や事象に即して、実際にどのような行動を起こしたり、どのような工夫を凝らし、どのような態度で問題解決に臨んだかを詳しく描写することのほうが大切であるという点です。その背景にある考え方は、人の行動を予測する最も有効な方法は、現在および近い将来の同一もしくは類似の環境下で、その人が現実に行動していること、もしくは行動しようとする意志をもっていることを確かめることである、というものです。
さらに言えば、内面的な性格、人柄、動機のような属人的な潜在能力よりも、特定の状況下で高業績を挙げた個人が実際に体現(embody, demonstrate)した観察可能な手本になるような行動(顕在能力)を明らかにすることによって、別の個人が同様の状況下でそれらの行動を反復模倣することで、間接的にせよその行動を誘発する潜在能力をも習得することが可能になり、それによって、個人のコンピテンシーをグループや組織全体のコンピテンシーを質的に高めることができるというのが、マクレランドの論点でした。
マクレランドに師事した米国ケース・ウエスターン・リザーブ大学(Case Western Reserve University)の社会心理学者ボヤティズ教授(Richard Boyatizis)は、マクレランド理論を発展させて、コンピテンシー理論の実証的体型を確立し、組織の人事管理上のツールとしての活用を可能にしました。1982年に著したThe Competent Manager: A Model for Effective Performance と題する著書のなかで、コンピテンシーを「特定の職務において効果的な高業績または結果として優れた行動に結びつけられる個人の特性」として、調査対象を12の組織、41種類の管理職責を担う約2000人に拡大し、彼らの業績とコンピテンシーの関係を精査し、コンピテンシーの測定方法と能力開発のモデルを紹介しています。その功績から、米国では“コンピテンシーの神様”として認められることになりました。
1990年代になると、従来の職務を定義する職務記述書の補完ツール、あるいは代替ツールとして、多くのアメリカ企業や組織で独自のコンピテンシー・モデルの構築を模索する動きが盛んになりました。それに呼応して、人事専門のコンサルティング会社も活発にクライアント企業内でのコンピテンシー・モデルの構築や評価方法の紹介を行うようになりました。各企業や組織に導入されるコンピテンシーには厳密な定義はなく、経営理念や組織風土によって当然のことながら細部での解釈には違いがあります。
しかし、概ね共通している定義は、前回紹介したとおり、観察・測定可能(measurable, assessable and observable)な知識・技能(KSAO)であることと、それらの知識・技能が高業績者と並みの社員との間で明確に区別できることの二つです。いずれにしても、コンピテンシー・モデルを導入する企業や組織の狙いは、経済成長が鈍化する成熟社会において、労働の質を高め、その結果として収益の質に拘り、低成長であっても持続性・発展性のある業績の挙げ方を大切にする経営理念を組織内に浸透させることにあると考えらます。

-
定森 幸生
Yukio Sadamori

- 1973年、慶應義塾大学経済学部卒業後、三井物産株式会社に入社。1977年、カナダのMcGill 大学院でMBA取得後、通算約11年間の米国・カナダ滞在を含め約35年間一貫して三井物産のグローバル人材の採用、人材開発、組織・業績管理業務全般を統括する傍ら、日本および北米の政府機関・有力大学・人事労務実務家団体・弁護士協会などの招聘による講演、ワークショップ、諮問委員会などで活躍。『労政時報』はじめ人事労務管理専門誌への寄稿・連載も多数。2012年に三井物産株式会社を退職後、グローバル・プラットフォーム設立。企業や大学の要請で、グローバル人材育成関連のセミナーやコンサルテーションを実施する一方、慶應ビジネススクール、早稲田ビジネススクールで、英語によるグローバル・ビジネスコミュニケーション講座を担当、実務家対象の社会人教育でも活躍中。