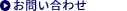グローバル HR ソリューションサイト
by Link and Motivation Group
- グループサイト
-
文字サイズ
2015.07.21
【チャオプラヤー川に吹く風(27)】タイシルク今昔 その1~伝統社会における織物
齋藤 志緒理

現代のタイシルク~無地の2色はクッションカバー、柄物の2枚はハンカチ。共にJim Thompson製(筆者撮影)
タイ国を代表する伝統的工芸は何か――といえば、筆頭に挙げられるのはタイシルクでしょう。タイシルクは外国人旅行者の土産品として人気があり、ネクタイやスカーフ、ポーチなど、各種製品が売られています。また、シルク生地で洋服を仕立てることもできます。
タイシルク製品は、外国人が求めるばかりでなく、タイ人が国外に持参する手土産としてもよく選ばれます。筆者自身、タイ人の友人からシルク製品をいただいたことが何度もあります。品質、デザイン性の高いタイシルクは、タイ人にとっても、自信をもって贈呈できるアイテムなのです。
このタイシルク――歴史を調べてみると、商業ベースで製品化され始めたのは、比較的最近であることがわかります。本連載では、今号から5回にわたり、タイの生糸生産や絹織物を巡る状況の推移を取り上げます。
●伝統社会における織物
タイの農村社会では、伝統的に絹や木綿の生産は女性が担っていました。女性は綿の栽培をし、養蚕用のカイコ蛾を採集し、草木を原料として染料を作り、川泥や植物からの抽出物や粘土を使って糸を媒染しました。
布を織ることは女性らしさにつながると考えられ、機織り技術の巧拙が妻として主婦としての評価にもつながりました。女児は幼児期から養蚕や糸紡ぎ、織り、染めの過程を観察し、少女になると母親や親戚の女性から機織りを教えられました。そして、結婚するまでに家庭用や儀式用の様々な織物の織り方を会得するのが一般的でした。男性たちは、織機や紡錘車など、織物生産のための道具は作ったものの、織り手にはなりませんでした。
なお、養蚕はモンスーンの雨が桑の若葉の成長を促す時期――ちょうど、田植えが終わった後の農閑期に行われます。
タイ国では、19世紀に合成の化学薬品が導入されるまで、植物染料と媒染剤にはもっぱら自然の物質が使われていました。合成染料がタイに伝えられた正確な年は定かではありませんが、20世紀中ごろまでには、人里離れた農村地域を除いて、一般的に合成染料が使われるようになったようです。
(スーザン・コンウェイ著『タイの染織』めこん刊 p.43, p.64-65, p.79)
●日本からの「お雇い技術者」の存在
上述のように、タイの伝統社会に浸透していた養蚕や機織りですが、その技術革新のために、明治期の日本人がタイ国に派遣されたことは、意外に知られていません。
明治末期、1902年から10年間、日本人養蚕技師の一団がタイ国の蚕業顧問として雇われました。吉川利治は「暹羅国蚕業顧問技師――明治期の東南アジア技術援助」(『東南アジア研究18巻3号, 1980年12月』)」で、その際の顛末を明らかにしています。
日本人技師の派遣/受け入れが実現した背景についてみると、タイ・日両国の立場は次のようなものでした。
<タイ側>=綿業や絹業は地方農家の副業として営まれ、ほとんどが自家消費用でした。宮廷を中心に絹の需要が増える中、タイ国の指導者にとっては、外国から多額の生糸や絹布を輸入しなくても済むよう、国内の養蚕業と織物業を育成、発展させることが現実的な課題でした。
<日本側>=1906~10年頃には、日本の生糸輸出量は、それまで世界最大の生糸輸出国だった中国の輸出量を上回り、世界第1位の座を獲得していました。当時東南アジアで唯一の独立国であったタイ国の独立維持を守るために、産業革命を成し得た日本が一役買うことは「東洋における先進国としての天職」であり、間接または直接に我が国の利益になる―という考え方がありました。
技師派遣に先立ち、1900年末に訪タイした専門家2名は、養蚕が盛んな東北タイに赴き、ナコンラーチャシーマー(通称:コーラート)を中心に調査を行いました。両名から報告を受けたと思われる当時の稲垣公使が「タイの生糸は品質が悪く、地元でしか用いられていない。しかし、養蚕業は広く行われており、改良を行えば、久しからずタイの生糸は有力な商品となる」旨の報告を、タイの内務大臣であり、ラーマ5世の王弟であるダムロン親王に進言したという記録が残っています。
次号では、日本人養蚕顧問が、タイで実際にどのような足跡を残したかを見てみましょう。

-
齋藤 志緒理
Shiori Saito

- 津田塾大学 学芸学部 国際関係学科卒。公益財団法人 国際文化会館 企画部を経て、1992年5月~1996年8月 タイ国チュラロンコン大学文学部に留学(タイ・スタディーズ専攻修士号取得)。1997年3月~2013年6月、株式会社インテック・ジャパン(2013年4月、株式会社リンクグローバルソリューションに改称)に勤務。在職中は、海外赴任前研修のプログラム・コーディネーター、タイ語講師を務めたほか、同社WEBサイトの連載記事やメールマガジンの執筆・編集に従事。著書に『海外生活の達人たち-世界40か国の人と暮らし』(国書刊行会)、『WIN-WIN交渉術!-ユーモア英会話でピンチをチャンスに』(ガレス・モンティースとの共著:清流出版)がある。