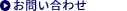グローバル HR ソリューションサイト
by Link and Motivation Group
- グループサイト
-
文字サイズ
2015.09.14
【チャオプラヤー川に吹く風(29)】タイシルク今昔 その3~日本人養蚕技師の活動(2)
齋藤 志緒理

象に曳かれた荷車の横で馬に乗る技師たち(写真提供:厚木市郷土資料館)
前号に続き、タイ国で1902年から10年間活動した日本人養蚕顧問たちの動向を紹介します。(参考文献:吉川利治「暹羅国蚕業顧問技師――明治期の東南アジア技術援助」(『東南アジア研究18巻3号, 1980年12月』)」
●蚕糸技術の普及と織物の改良
前号で述べたように、養蚕顧問の外山亀太郎ら日本人技師は、バンコクと東北のナコンラーチャシーマー県(通称:コーラート)、その隣県のブリーラム県に拠点を置いて活動していました。コーラートでは桑樹が生長し、蚕の大量飼育が可能になったため、外山は、製糸・織物の技術改良を目指すべく「模範製糸場」の建設を起案します。しかし、それをどこに作るかで議論がおこります。
日本人養蚕顧問は、「繭が大量に生産され、水質がきれいで、低賃金の女子労働者を得やすいコーラートに作るべき。彼らの技術向上と所得増にもつながる」と主張したのに対し、タイ政府側は「先行投資の回収、国家の財源確保を考えれば、辺鄙な地方に設置する必要はない」とバンコク設置論を唱えました。結局、専門家である日本人の意見が受け入れられ、1905年にコーラートに模範製糸場を創設。翌1906年にはブリーラムでも実習生を集めて、繭の飼育や繰糸法を教え始めました。
コーラートやブリーラムから、住民に教えられるだけの技能を習得した卒業生が出ると、東北タイの8カ所に設置した支所に派遣して、知識の普及を図りました。その際、繭は蚕業局が買い上げ、住民に座繰機械で生糸を作らせました。出来上がった生糸は蚕業局のものとなりますが、習熟した住民には日本製の座繰機械を1台ずつ配布する――という方法をとりました。
結果は予想以上の反響で、1906年に講習を受けにきた住民は、材料の繭を使い切るまでの3カ月間で126人。その内61人が座繰機械の配布を受けました。そして1910年までに各支所で配布した座繰機械は1159台に上りました。
こうして蚕糸の生産技術が底上げされると、日本人技師らは、次に織物の改良に着手しました。1908年、織物教師として飯塚亀吉・ハナの父娘が2年契約でコーラートに赴任します。(娘のハナは到着して間もなく病死。)その際、日本製の織機10台が輸入され、各種絹織物1700枚以上が織られました。しかし、織機の値段は座繰機械のように安価ではなく、織り方に習熟するにも数年かかります。織りの改良に関しては、目に見えた成果が出ぬまま、日本人養蚕顧問らが帰国の日を迎えることになります。
●日本人蚕業顧問の帰国
日本人蚕業顧問のよき理解者であり、終始その活動を支えたのは、ラーマ5世(チュラロンコン王)の38番目の王子、ペンパタナポン親王でした。イギリスで農学を学んだ同親王は、蚕業局創設以来、局長を務めますが1909年に26歳の若さで病死してしまいます。翌1910年にはラーマ5世も崩御。悪いことは重なるもので、この年は天候不良のため桑の生育が悪く、蚕病が発生し、住民に配布した蚕種が半分も死んでしまう事態となりました。
こうした中、組織の改組が行われ、養蚕試験場の外国人所長は廃止、他のほとんどの職員は配置換えとなりました。そして地方産業に関する部局は農務省から内務省に移管されました。
1911年、最後まで残っていた横田技師と織物教師の飯塚がコーラートを去りました。その後、1913年には「蚕糸業への投資は採算が合わない」という理由で、各地の試験場や支所は廃止されるに至ります。外山らが日本種とタイ種を掛け合わせて品種改良に努めた蚕も、不十分な設備と技術者不足のため、良品種を他種から隔離して増産することができず、1911年頃には飼育されている蚕は全てタイ種に戻り、日本種は消滅してしまいました。
●日本人蚕業顧問への評価
日本人技師による養蚕開発や蚕糸改良事業には厳しい批判もありました。永年タイ国の農務省顧問を務めた英国人、ウォルター・グラハムは自著で、「実習を受けた娘たちは、家に帰れば、新知識はかなぐり捨て、相変わらずの方法に回帰し、配布された日本製器具は屋根裏に祭り上げられている。日本人専門家の努力にも関わらず、1922年の絹を巡る状況は、開発に着手する前の1901年と同じ」と断じています。
これに対し、日本人技師の教え子で、横田と共に働いたタイ人のプラヤー・アーハーンボーリラックは「新式の面倒な機械より、先祖伝来の簡便なものが好まれたのも一部事実だが、新式の繰糸器具を使おうとした者も少なからずいた。新式の機械で生産した生糸は良質だったので、住民は自分らで織り上げ、高い値段で買い上げてくれる蚕業局に売却したため、市場に出回らなかったのだ。また、蚕業局が住民を指導したのはわずか4年であり、この年数で住民の意識を変えられるものではない」と発言しています。
本論文の著者である吉川利治は「タイの独立維持、殖産興業に手を貸そうとした日本人外交官・稲垣の呼びかけに、チュラロンコン王やダムロン親王は、日本側の計画通りに資金を出し、全ての進行を日本人に委ねるという鷹揚さで応じた。その背景には、蚕糸業の発展による日本の『富国強兵』という手本があった。ただ、不幸なことに日本側はタイの気候風土、住民の国家意識、気質を知らず、タイ側は養蚕開発の難しさを知らなかった。資金の乏しいタイ国は、現実的に対処しなければならず、10年かけて採算がとれなければ、打ち切らざるを得なかったのだろう」と分析しています。
●考察
日本人養蚕顧問らは、10年間でタイの養蚕開発を飛躍的に前進させることはできませんでしたが、彼らが礎を築いた養蚕学校、農学校の卒業生は農務省幹部となり、その後の養蚕業や農業行政を支えていきました。「お雇い外国人」として20世紀初頭にタイ国に赴任した日本人がいたという事実は、日タイの交流史の中で、もっと思い起こされてよいのではないでしょうか。
模範製糸場をどこに作るか――の議論では、東北タイのコーラートを推した日本人、「辺鄙な地方に設置する必要はない」としたタイ政府側の思惑の違いが浮き彫りになりました。
そもそも外山らが養蚕事業の現場として選んだ東北タイは、1892年までタイ政府が直接統治する地域ではなかったこともあり、20世紀初頭当時の住民が国家への帰属意識をもっていたとは言えません。タイ中央の人々にとっても、東北タイは心理的に遠い地域であり「辺鄙な地方」という表現からはそんな意識が透けて見えます。
しかし、こと養蚕に関して、タイ全土の中で東北タイは昔も今も、紛れもない中心地。日本人技師らは、土地性を重視して同地で事業を展開しました。その判断の中に、100年以上前に日本人として国際協力の先陣を切った人々の現実主義的、合理的姿勢をみる思いがします。
さて、次号では、時代下って、第二次世界大戦後――「タイシルク王」と呼ばれたある著名なアメリカ人の足跡に光を当てます。

-
齋藤 志緒理
Shiori Saito

- 津田塾大学 学芸学部 国際関係学科卒。公益財団法人 国際文化会館 企画部を経て、1992年5月~1996年8月 タイ国チュラロンコン大学文学部に留学(タイ・スタディーズ専攻修士号取得)。1997年3月~2013年6月、株式会社インテック・ジャパン(2013年4月、株式会社リンクグローバルソリューションに改称)に勤務。在職中は、海外赴任前研修のプログラム・コーディネーター、タイ語講師を務めたほか、同社WEBサイトの連載記事やメールマガジンの執筆・編集に従事。著書に『海外生活の達人たち-世界40か国の人と暮らし』(国書刊行会)、『WIN-WIN交渉術!-ユーモア英会話でピンチをチャンスに』(ガレス・モンティースとの共著:清流出版)がある。